ワンちゃん・ネコちゃん相談室 Consultation room


獣医師執筆

森のいぬねこ病院グループ院長
日本獣医学会、動物臨床医学会、獣医がん学会所属
西原 克明(にしはら かつあき)先生
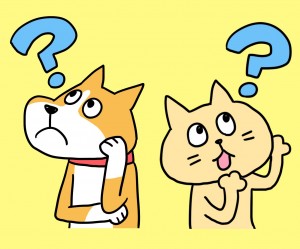
もともと『ステロイド』とは、厳密には化学分野の用語で、ステロイド核という構造を持った化合物のことを言います(難しい!!)。
ですが、日常、私たちが使う『ステロイド』とは、ステロイドホルモンやステロイド薬、その中でも『副腎皮質ホルモン』と呼ばれるホルモンや副腎皮質ホルモンと似た作用を持つ薬のことを指します。
ここでは、難しい定義ではなく、『副腎皮質ホルモンと似た作用を持つ薬』のことをステロイドとして扱うことにします。
そもそも副腎皮質ホルモン(コルチコステロイドとも呼ばれます)とは、副腎と呼ばれる臓器(腎臓の傍にある小さな臓器です)から分泌されるホルモンのことです。つまり、元々は体から分泌される物質なのです。
それがお薬という視点から見ると、実に様々な作用を持っていることがわかり、今現在は実際に薬として利用されています。
その作用とは、炎症を鎮める効果(抗炎症効果)、痒みを鎮める効果、免疫反応を抑える効果(免疫抑制効果)、がんの進行を遅らせる効果(抗腫瘍効果)などがあり、さらには体液のバランスを調整する効果や糖やたんぱく質、脂肪の代謝にも影響を与える効果を持っています。
しかし、これらの作用は効きすぎた場合、逆に副作用を引き起こすため、ステロイド薬の使用にあたっては、十分な注意が必要です。
また、ステロイド薬は、体から分泌される天然の副腎皮質ホルモンよりも、より強力に炎症を抑えたり、あるいはより作用時間が長いものなど、様々な特徴を持った合成ステロイド薬が開発されています。
ステロイド薬の形状は、飲み薬や塗り薬、あるいは喘息の時に使う吸入薬などたくさんのものがあり、これらは、病気の状況によって使い分けられます。
皮膚炎の時は塗り薬もしくは飲み薬を使います。
その他の病気では基本的に飲み薬になりますが、外耳炎や結膜炎のような炎症に対しては、点耳薬、点眼薬といった形状のステロイド薬が使われています。
また、お薬の中には、ステロイドと抗生物質など他のお薬を合わせて、一剤で投与できるタイプもあります。
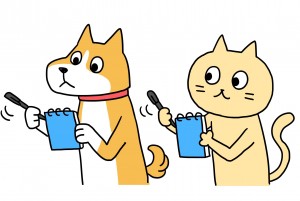
ステロイドは前述のとおり、様々な作用を持っていますので、多くの病気で使用されています。
皮膚の炎症では、湿疹などの見た目の症状に加え、『かゆみ』が症状としてみられ犬を苦しめます。かゆみは炎症の結果として起こるものなので、ステロイドの抗炎症作用を利用することで炎症を抑え、痒みを止めることができます。
また、皮膚炎の原因には、アレルギーやアトピー、さらには細菌や真菌(カビ)、寄生虫(ノミ、ダニ)などによる感染がありますが、感染性の皮膚炎では、ステロイドを使用することで、感染を悪化させることがありますので、皮膚炎での使用にあたっては、正しい診断を受けることが重要です。
皮膚炎以外にも、気管炎や気管支炎、肺炎、鼻炎、関節炎、脳炎、肝炎、腎炎、など多くの炎症性の病気が存在しますが、それらの炎症を抑えるためにステロイドが用いられます。
しかし、ステロイドの抗炎症作用は、対症療法、つまり症状を軽減させているだけで、決して根本的に治しているわけではありません。そのため、ステロイドに頼りすぎていると、いつまでたってもステロイドを使い続けることになり、様々な副作用の問題が出てきてしまいます。
ですので、炎症性の病気でステロイドを使うときには、根本的に病気を治すための治療も同時に行うことが重要です。
病気の中には、自分で自分の体を攻撃してしまう『自己免疫性疾患』と呼ばれるものがあります。自分で自分の皮膚を攻撃して皮膚炎を引き起こす天疱瘡、赤血球系を攻撃して貧血を引き起こす免疫介在性溶血性貧血、あるいは血小板系を攻撃する免疫介在性血小板減少症、さらには関節リウマチや全身性エリテマトーデスと呼ばれる病気なども自己免疫性疾患に含まれます。
これら自己免疫性疾患の治療に、ステロイドの免疫抑制作用が利用されます。それによって、自分で自分の体を攻撃してしまう免疫反応を止めることができるため、症状を改善させることができます。
しかし、ステロイドが免疫抑制作用を発揮するには、多量のステロイドを投与しなければならず、その分副作用のリスクも非常に高くなってしまいます。そのため、現在では、自己免疫性疾患に対しては、ステロイドだけでなく様々な免疫抑制剤も利用されています。
また、免疫反応とは本来、細菌やウイルスなど外から侵入してきた異物を排除するためのものですが、免疫抑制作用によって、その本来の免疫反応も弱ってしまいます。そのため、細菌感染などの合併症が起きやすくなるため、多くの場合は、抗生物質などのお薬を併用します。
最初に述べたように、ステロイドは、元々は副腎で分泌する副腎皮質ホルモンのことです。
その副腎皮質ホルモンがうまく分泌できなくなる病気がアジソン病で、本来自分で分泌するべき副腎皮質ホルモンの代わりにステロイドを補うことで、症状をコントロールすることができるようになります。
ステロイドは、がんの中でもリンパ腫と肥満細胞腫と呼ばれるがんに対して、非常に効果を発揮します。
リンパ腫では、ステロイドの投与により、大きくなったリンパ節を小さくする効果があります。また、リンパ腫によって生じた様々な臨床症状も軽減させることができます。
しかし、ステロイドによるリンパ腫への改善作用は一時的なもので、決して余命を伸ばすものではありません。
そのため、現在の獣医療では、リンパ腫の治療はステロイド単独で使用するのではなく、その他の抗がん剤も一緒に用いる『多剤併用療法』によって治療することがほとんどです。
肥満細胞腫では、炎症反応に関わる肥満細胞ががん化して増殖するのですが、ステロイドはその肥満細胞の増殖を抑える効果を発揮します。
実際には、肥満細胞を直接小さくする作用を狙って投与する場合と、外科手術によって肥満細胞腫を切除した後の再発予防を目的として投与する場合があります。
肥満細胞腫の中には、ステロイドだけで長期間、再発を予防できるタイプもありますが、やはりほとんどのケースでは、リンパ腫と同じように、ステロイドに加えて他の抗がん剤を併用する多剤併用療法が用いられます。
また、リンパ腫や肥満細胞腫以外のがんでも、がん自身が引き起こす炎症反応を抑える目的で、ステロイドを使用することがあります。
これら腫瘍性疾患でステロイドを用いる場合は、ステロイドが急激にその作用を発揮すると、逆に体への負担が大きくなり『腫瘍溶解性症候群』という重篤な合併症が起こることがあります。そのため、投与にあたっては十分な注意が必要です。
また、自己免疫性疾患同様、がんに対してステロイドを用いる場合は大量かつ長期的に投与することになりますので、その副作用や合併症のモニターをしっかりと行うことが重要です。

ステロイドは、病気に対する効果は非常に強く、多くの疾患に用いられる反面、使い方を誤ると、副作用に悩まされることになります。
そのため、ただ漫然と使用するのではなく、その注意点をよく理解した上で使うことが大切です。
「ステロイドは恐ろしい薬」というイメージをお持ちの方も多いかもしれませんが、その理由のほとんどがステロイドは対症療法の薬にも関わらず、「治った」と勘違いしてしまうことが原因です。
どういうことかと言いますと、例えばアトピー性皮膚炎で、ステロイドを使うとかゆみや炎症がみるみる改善し、一見『治った』ように感じてしまいます。
しかし、ステロイドはかゆみや炎症を抑え込んでるだけで、その原因を改善しているわけではありません。そのため、ステロイドで皮膚が良くなっても、そこでステロイドを止めてしまうと、すぐに再発してしまうのです。
そしてその後、再発したらステロイド→症状が治まったら止める→また再発したらステロイド、という悪循環を繰り返し、そのうちステロイドが手放せなくなり、ステロイドの長期投与による様々な副作用に苦しむことになるのです。
ですので、ステロイドを使うときは、あくまで『ステロイドは対症療法』ということをしっかり認識して、病気の原因を治していく治療を一緒に進めていくことが重要です。
しかし、中にはアトピーや自己免疫性疾患のように現代の医療では原因を治せない病気もあります。
その場合は、他の薬や日常生活の管理などで、できるだけステロイドの投与量を減らすことで、副作用のリスクを軽減させることも可能です。
また、飲み薬よりも塗り薬の方が副作用は出にくくなりますので、可能な場合は塗り薬、点眼薬、点耳薬など局所的に投与するステロイドを使うと良いでしょう。
ただし、これらのステロイドも長期間使いすぎると副作用は見られますので、注意しましょう。
ステロイドを投与することで、様々な副作用が生じますが、全身的には、多飲多尿(たくさんの薄い尿をするようになり、その分お水をたくさん飲むようになる症状)、食欲増進といった症状が見られるようになります。
さらには長期間の投与で、皮膚が薄くなったり、場合によっては石灰化という状態になることもあります。
また脱毛、筋肉の衰え、内臓脂肪の増加(見た目には、ポットベリーと呼ばれる下っ腹が出た状態)なども認めるようになります。
さらに免疫抑制作用が続くと、細菌や真菌などによる感染症が生じ、元気食欲がなくなったりすることもあり注意が必要です。
また、血液検査上では、白血球や肝臓関係の数値が上昇したり、貧血や血糖値、カルシウムなどの数値が変化しますので、定期的にチェックするようにしてください。
その他にも多くの症状が見られるようになりますが、まずは上記のような症状が表れた時には、漫然と使用せず、かかりつけの獣医師に状況を相談するようにしましょう。

このように、ステロイドは多くの病気に対して、非常に有効に働く薬です。
しかしその一方で、ステロイドは対症療法の薬であり、決して根本的な治療を行う薬ではないこと、さらには使い方によっては重大な副作用を持つことが問題となります。
そのため、アトピーやリウマチ、あるいはリンパ腫や肥満細胞腫といった、長期的にステロイドを使う病気に対しては、なるべくステロイドの使用量を減らすこと、あるいはステロイドの副作用を軽減させることも重要になります。
当院では、具体的には以下の三点に取り組むことが多いです。

例えば自己免疫性疾患では、ステロイドの免疫抑制作用によって治療しますが、他の免疫抑制剤を併用することで、ステロイドの使用量を減らすことができます。
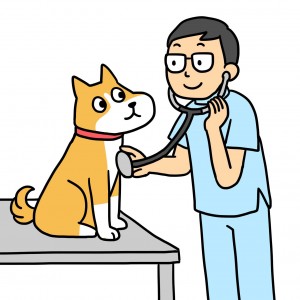
例えばアレルギー性皮膚炎では、アレルギー反応を起こしてしまう食材を避けることで、皮膚の症状を軽減させることができ、その結果ステロイドの使用を抑えることができます。

アトピー性皮膚炎では、体内の免疫細胞のバランスが崩れていることが知られています。
それに対して、インターフェロン療法を用いることで、免疫細胞のバランスが整えられ、さらにはかゆみなどの症状に対する改善効果があり、その分ステロイドの使用量を減らすことができます。
またアガリクスなどの免疫力をアップさせるサプリメントにも、アトピーやアレルギーなどの皮膚炎に対して、同じような効果が期待できます。
さらにはがんの進行を抑える作用も期待できるため、私個人の使用経験として、実際にそれらの病気に対して効果が見られた時には、ステロイドの使用量を抑えることができています。
さらには、ステロイドとアガリクスを併用することで、ステロイドや抗がん剤の副作用を抑える効果も期待できるため、特に腫瘍疾患に対しては、アガリクスを積極的に併用するようにしています。
このように、ステロイドの効果を最大限発揮するために、その他の治療方法を組み合わせ、なるべくステロイドの副作用を抑えることが重要です。
【PR】ペット用キングアガリクス100
皮膚・毛並みが気になるワンちゃん、ネコちゃんに対する飼い主様満足度82.5%、獣医師の満足度84.6%
露地栽培アガリクス100%で製品化した高品質サプリメント 無料の味見用サンプルを2粒プレゼント中
執筆者

西原 克明(にしはら かつあき)先生
森のいぬねこ病院グループ院長
帯広畜産大学 獣医学科卒業
略歴
北海道、宮城、神奈川など様々な動物病院の勤務、大学での研修医を経て、2013年に森のいぬねこ病院を開院。現在は2病院の院長を務める。大学卒業以来、犬猫の獣医師一筋。
所属学会
日本獣医学会、動物臨床医学会、獣医がん学会、獣医麻酔外科学会、獣医神経病学会、獣医再生医療学会、ペット栄養学会、日本腸内細菌学会
皮膚・毛並みが気になるワンちゃん、ネコちゃんに対する飼い主様満足度82.5%、獣医師の満足度84.6%
© 2025 ケーエーナチュラルフーズ株式会社